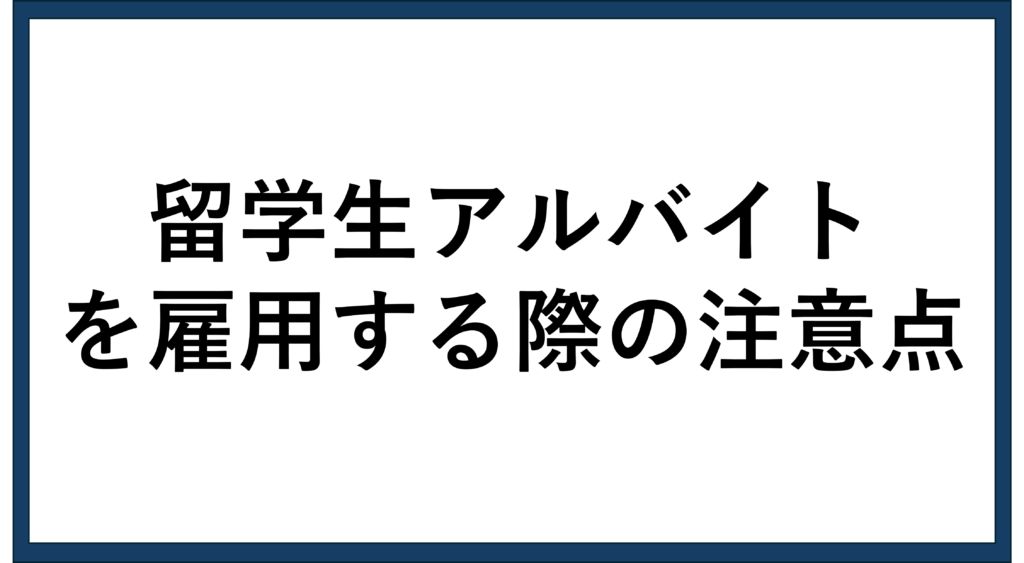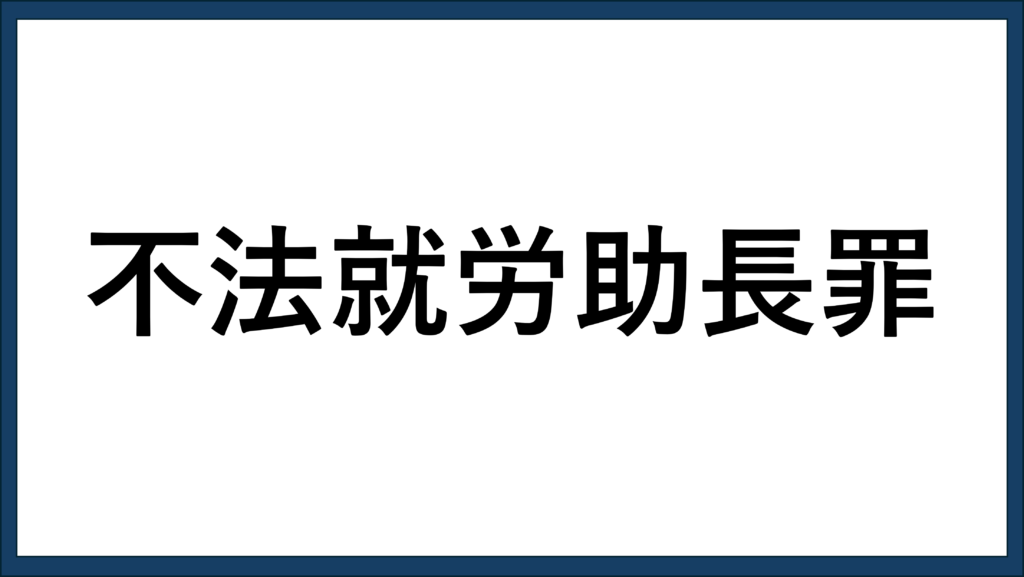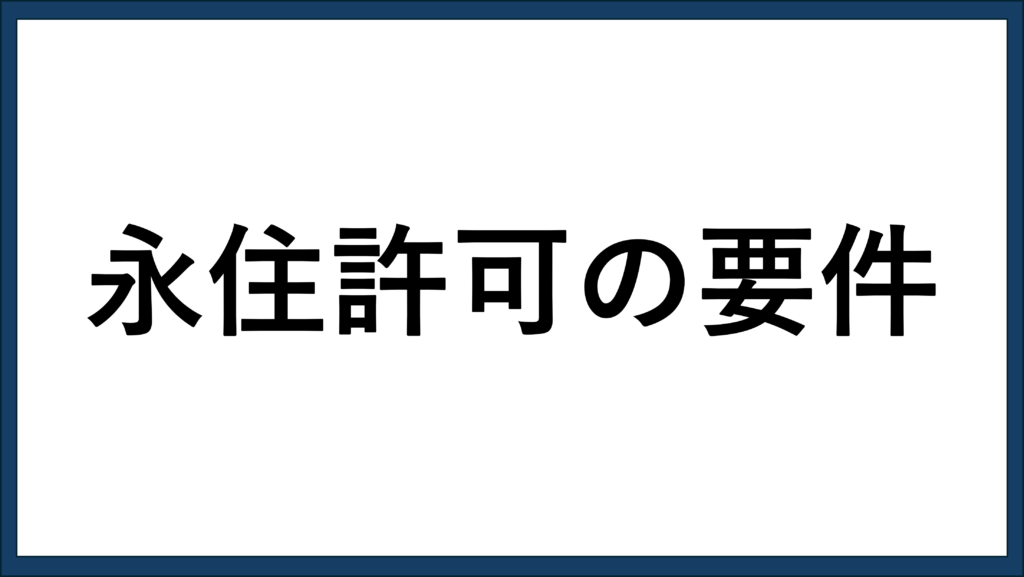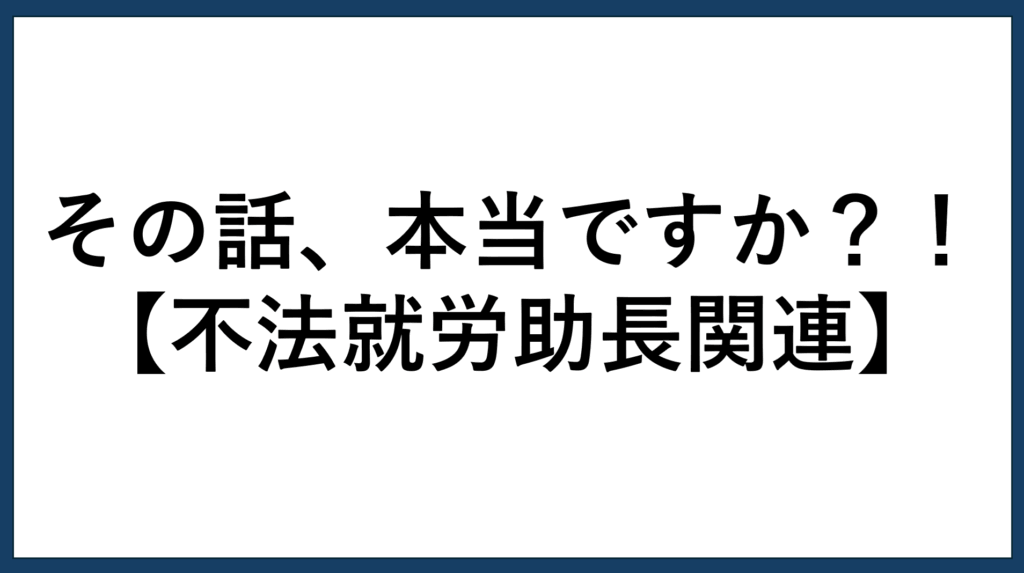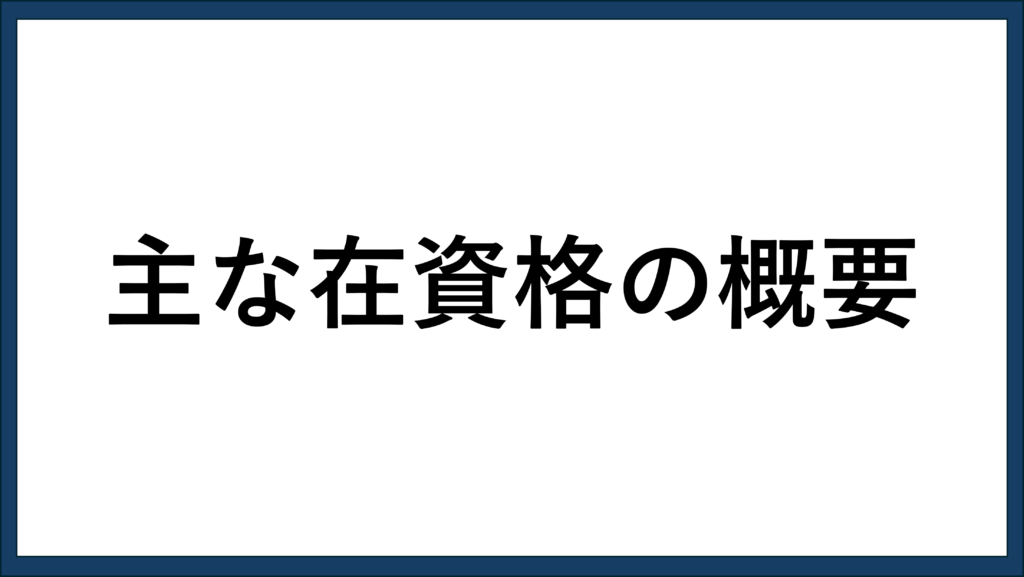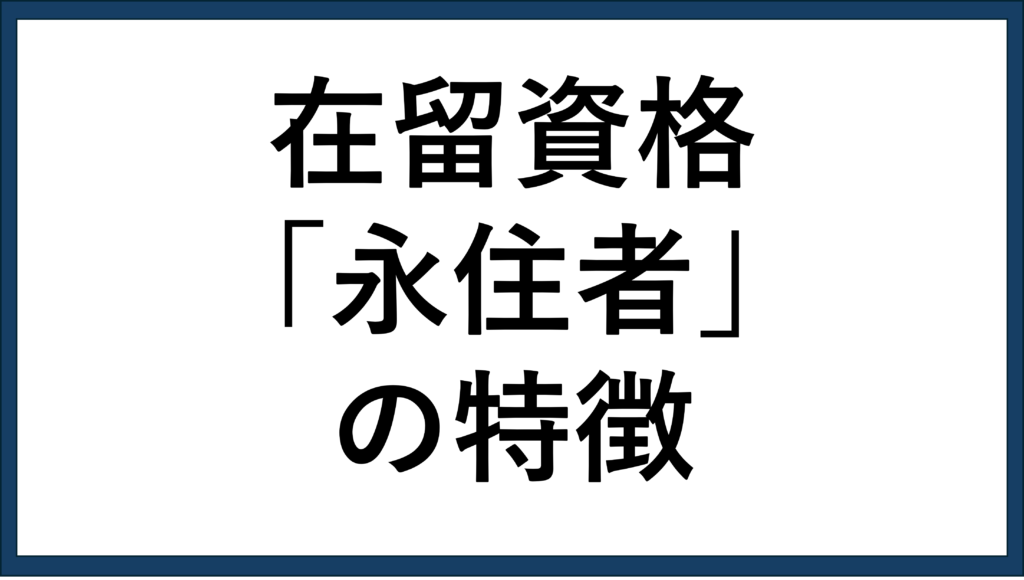-1024x577.png)
令和7年3月14日付で、出入国在留管理庁のホームページに出入国管理に関する各種統計資料が発表されました。
出入国在留管理庁のホームページ
令和7年のプレスリリース | 出入国在留管理庁
今回は、「令和6年(2024年)末における在留外国人数について」の資料から「在留外国人数」について見ていきます。
在留外国人数(全国)~入管発表資料
日本全体で在留外国人数がどれくらいいるのかを見てみましょう。
まず全体数については、
令和6年末現在における中長期在留者数は、349万4,954人、特別永住者数は、27万4,023人で、これらを合わせた在留外国人数は、376万8,977人となり、前年末(341万992人)に比べ、35万7,985人(10.5%)増加しました。
とあります。
ここで用語について少し補足します。
「中長期在留者」「特別永住者」とは?
「中長期在留者」とは、簡単に言うと3か月を超えて日本に滞在できる在留資格を持つ人たちです。
例を挙げると、留学生(一般的に在留資格「留学」)や技能実習生(在留資格「技能実習」)、会社員(在留資格「技術・人文知識・国際業務」など)、会社経営者(在留資格「経営・管理」)の人などが一般的に中長期在留者に当たります。通称「観光ビザ」などと呼ばれる観光や親族訪問などの際に取得する在留資格「短期滞在」は、ここでいう「中長期在留者」には当たりません。
「特別永住者」とは、簡単に言うと先の戦争時に日本に住んでいた韓国人などで日本に永住している人です。
在留外国人数は、過去最高を更新!
中長期在留者数と特別永住者数を合計した在留外国人数は、
376万8,977人(2024年末現在)
で、過去最高を更新しています。
前年末から約36万人増加していますが、この増加の主な要因は「中長期在留者数」の増加によるものです。
なお、2024年末現在の中長期在留者数は349万4,954人です。
「中長期在留者数」について、その推移を見てみると以下になります。
| 【年末】 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 中長期在留者数 | 約279万人 | 約313万人 | 約349万人 |
コロナ禍以降、毎年30数万人増加している傾向にあることがわかります。
国籍・地域別の在留外国人数
国籍・地域別の在留外国人数について見てみます。
なお、「地域別」とあるのは、日本が承認していない国を「地域」で呼んでいるからです。台湾、パレスチナなどがこれに当たります。
在留外国人数が多い上位10つの国・地域を並べると以下のようになります。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 中国 | ベトナム | 韓国 | フィリピン | ネパール |
| 約87万人 | 約63万人 | 約40万人 | 約34万人 | 約23万人 |
| +約5万人 | +約7万人 | ー約1千人 | +約2万人 | +約5.7万人 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ブラジル | インドネシア | ミャンマー | 台湾 | 米国 |
| 約21万人 | 約20万人 | 約13万人 | 約7万人 | 約6.6万人 |
| +67人 | +約5万人 | +約4.8万人 | +約5千人 | +約3千人 |
<補足>上表の下段は、前年末からの増減した人数です。
上記の米国に続けて在留外国人数の多い順に国・地域を並べると、
タイ、スリランカ、インド、ペルー、バングラデシュ、パキスタン、カンボジア、朝鮮、モンゴル、英国
となっています。
また、上位10つの国・地域を見てみると、
中国、東南アジアの国々(ベトナム・フィリピン・インドネシア・ミャンマー)、ネパールの人々の増加が顕著です。
増加数が大きかった国籍について、次にまとめました。
令和5年(2023年)末の在留者数から増加が著しかった国
入管公表資料には、表「国籍・地域別 在留外国人数の推移」において、「対前年末増減率(%)」という指標があります。
この対前年末増減率というのは、前年末の人数から何パーセント増減したのかを表しています。
例えば、令和5年(2023年)末に100人、令和6年(2024年)末に110人だった場合、この対前年末増減率は+10%となります。「100人から10%増えて、110人」というものです。
入管公表資料「在留外国人の推移」において、この対前年末増減率、つまり令和5年(2023年)末からの増減率について、増加率が大きかった上位10つの国を並べると以下のようになります。(増加数が大きかった順になります。)
1.ミャンマー +55.5%
2.スリランカ +35.2%
3.インドネシア +34.0%
4.ネパール +32.2%
5.バングラデシュ +25.4%
6.パキスタン +17.0%
7.カンボジア +13.0%
8.ベトナム +12.3%
9.インド +10.5%
ミャンマーが2023年末の在留者数に対して、50%以上の増加となっています。
(ミャンマー:【2023年末】約8万6千人 【2024年末】約13万5千人)
ミャンマーは、2021年に国軍によるクーデターの発生により、本国情勢が不安定な国です。
では、どの在留資格を持って日本に在留するミャンマー人が増えたのかを見ていきます。
どの在留資格を持つ人が1年間でどのくらい増えたのかを調べてみる
今回、ミャンマーを例に挙げて見ていきますが、その他の国についても同様に見ていただければ、どの在留資格を持つ人が増えているのかが分かります。
まず、入管ホームページの「広報・情報公開等>プレスリリース」より、「令和5年末現在における在留外国人数について」と「令和6年末現在における在留外国人数について」というページがあり、それぞれのページに「【令和5年末】公表資料」と「【令和6年末】公表資料」がありますので、それぞれを対比して見ていきます。
出入国在留管理庁ホームページ
【令和5年末】公表資料 001415139.pdf
【令和6年末】公表資料 001434755.pdf
各資料に「【第2表】国籍・地域別 在留資格別 在留外国人数」という表があります。
それぞれの年の増加が大きい在留資格別の人数を見てみると、以下のようになります。
| 技能実習 | 技術・人文知識・国際業務 | 留学 | 特定技能 | 特定活動 | |
| 令和5年末 | 26,352 | 10,511 | 12,177 | 11,873 | 15,983 |
| 令和6年末 | 35,844 | 14,000 | 23,290 | 27,348 | 22,720 |
| 増加人数 | +9,492 | +3,489 | +11,113 | +15,475 | +6,737 |
在留資格「特定技能」は、「技能実習」を終了した元技能実習生や留学生が「特定技能」へ在留資格を変更したり、本国から直接日本に就労をするために来た人が持つ在留資格です。在留資格「技能実習」と「留学」が増加していることからも、今後「特定技能」の人数が増えていくと考えられます。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、エンジニアや経理などの学術的素養を背景とした仕事に就く人が持つ在留資格です。在留資格「留学」が増えていることから、現在は留学生で、今後大学などを卒業した後に日本の会社に就職する人も増加し、この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人も増えていくと考えられます。
在留資格「特定活動」は、その時々の時勢を考慮し、特定活動の内容が設けられています。
現在、ミャンマー国内の情勢を考慮した在留ミャンマー人への緊急避難措置として、この「特定活動」が設けられています。この緊急避難措置は、留学生で学校を卒業後、日本の会社に就職することなく本来は帰国する人などの継続在留を認めるものです。過去には、コロナ禍における継続在留を認めるものなどもありました。
東南アジアの国々やネパールの人の在留資格の特徴
昨今、在留者が増加しているベトナム、インドネシア、ミャンマーなどの東南アジアの国々やネパール、スリランカの人の在留資格の特徴を見てみます。
前記したようなミャンマー人の特定活動の増加やフィリピン人は永住者が多く、在留資格「留学」は少ないなど、その国ごとに相違点はありますが、概ね
在留資格「技能実習」「技術・人文知識・国際業務」「留学」「家族滞在」「特定技能」
のいずれかの割合が多い傾向です。
本国から在留資格「技能実習」「特定技能」「留学」などの在留資格を持ち日本に在留することもあれば、
在留資格「技能実習」⇒「特定技能」
在留資格「留学」⇒「技術・人文知識・国際業務」又は「特定技能」など
のように在留資格変更により、継続して在留していくケースがあり、今後も在留外国人数(中長期在留者数)は増加すると考えられます。
また継続した在留に伴う在留者の家族の呼び寄せなどで、今後さらに「家族滞在」も増えていくと考えられます。
おわりに
以上、在留外国人数について、解説を加えながら見ていきました。
詳細をお知りになりたい方やご興味がある方は、入管ホームページをご覧ください。
別記事となりますが、在留外国人数についての記事をさらに書きたいと思っています。
外国人共生活動に関心がある私ですが、日本人と外国人の相互理解において、本記事が少しでもお役に立てたら幸いです。
本記事の内容を動画にしました。よろしければご参照ください。
https://youtu.be/yRn5izsxjsk?feature=shared
ひぐち行政書士事務所ホームページ